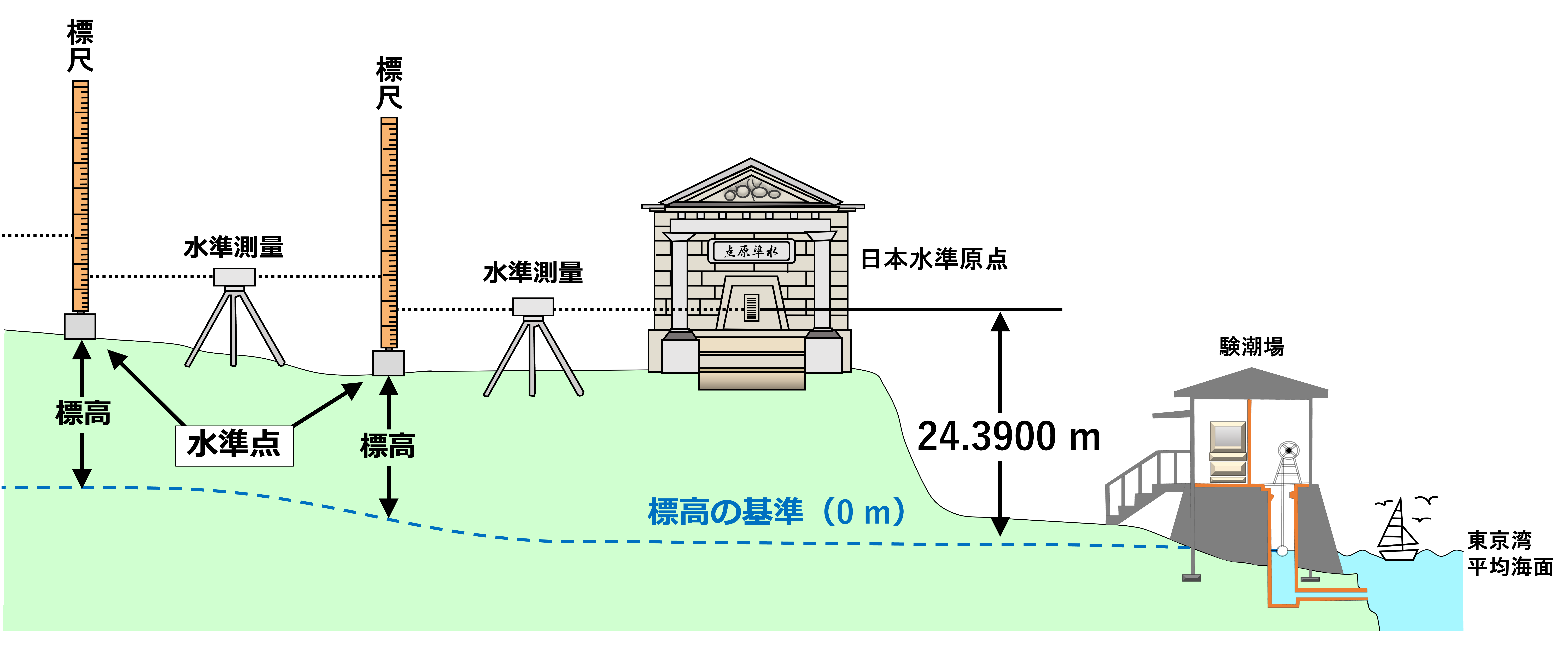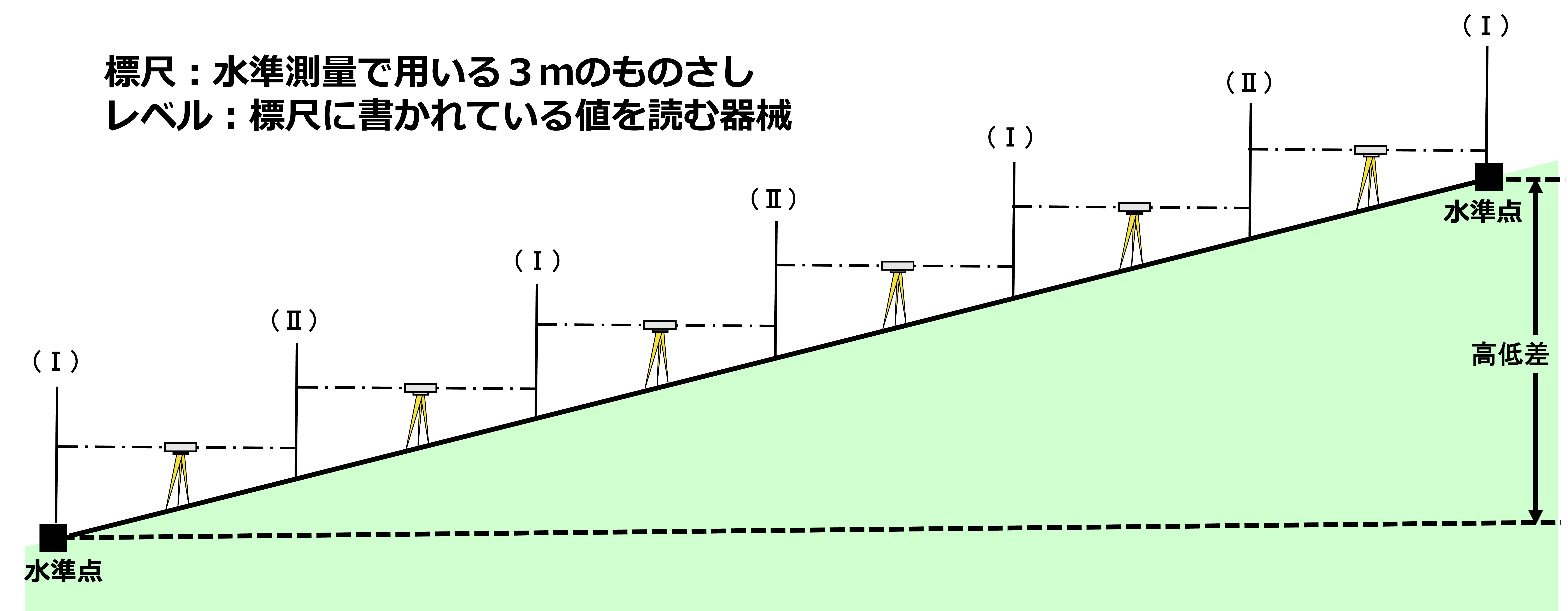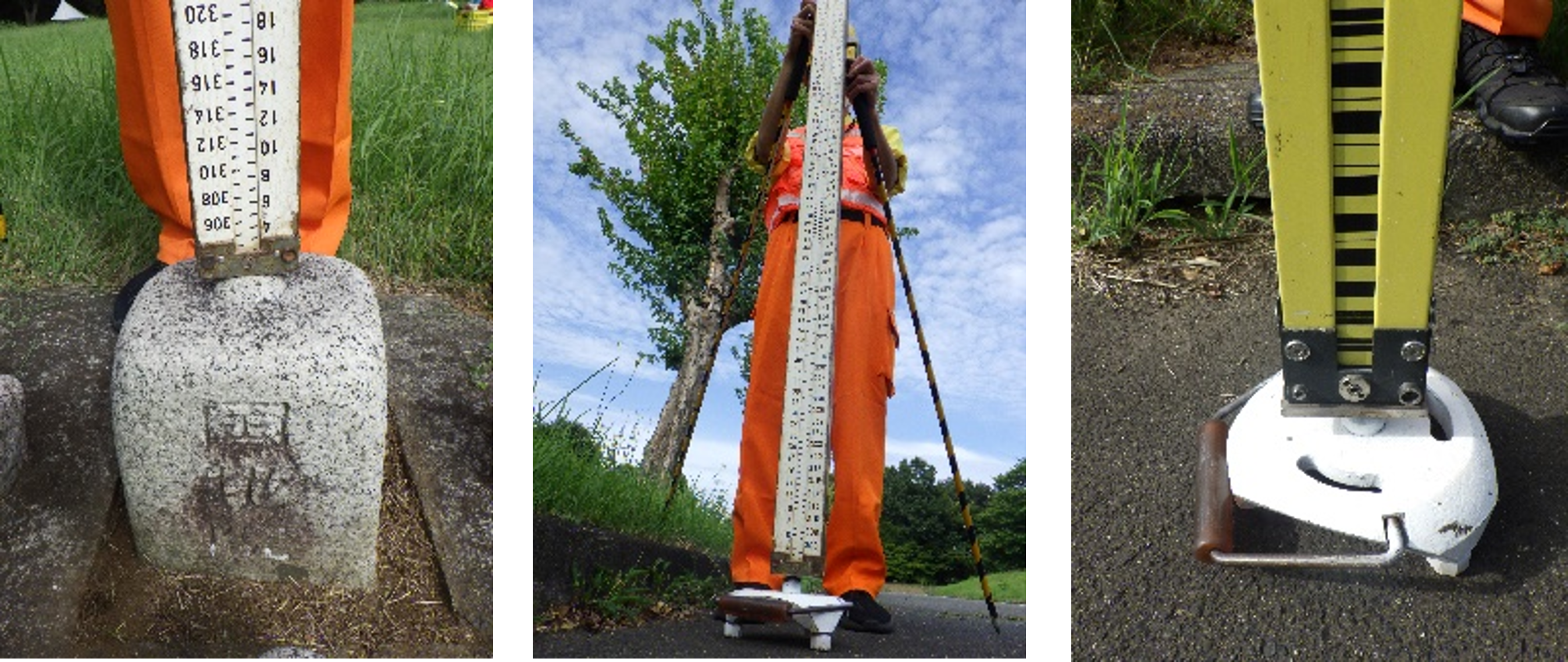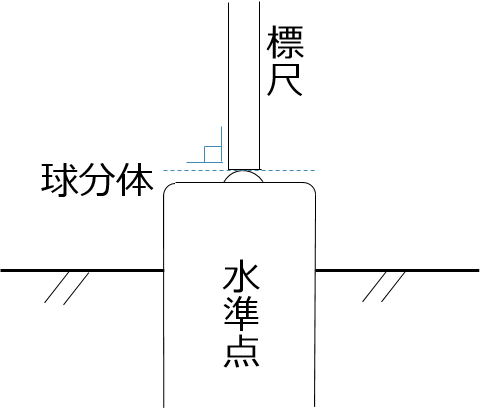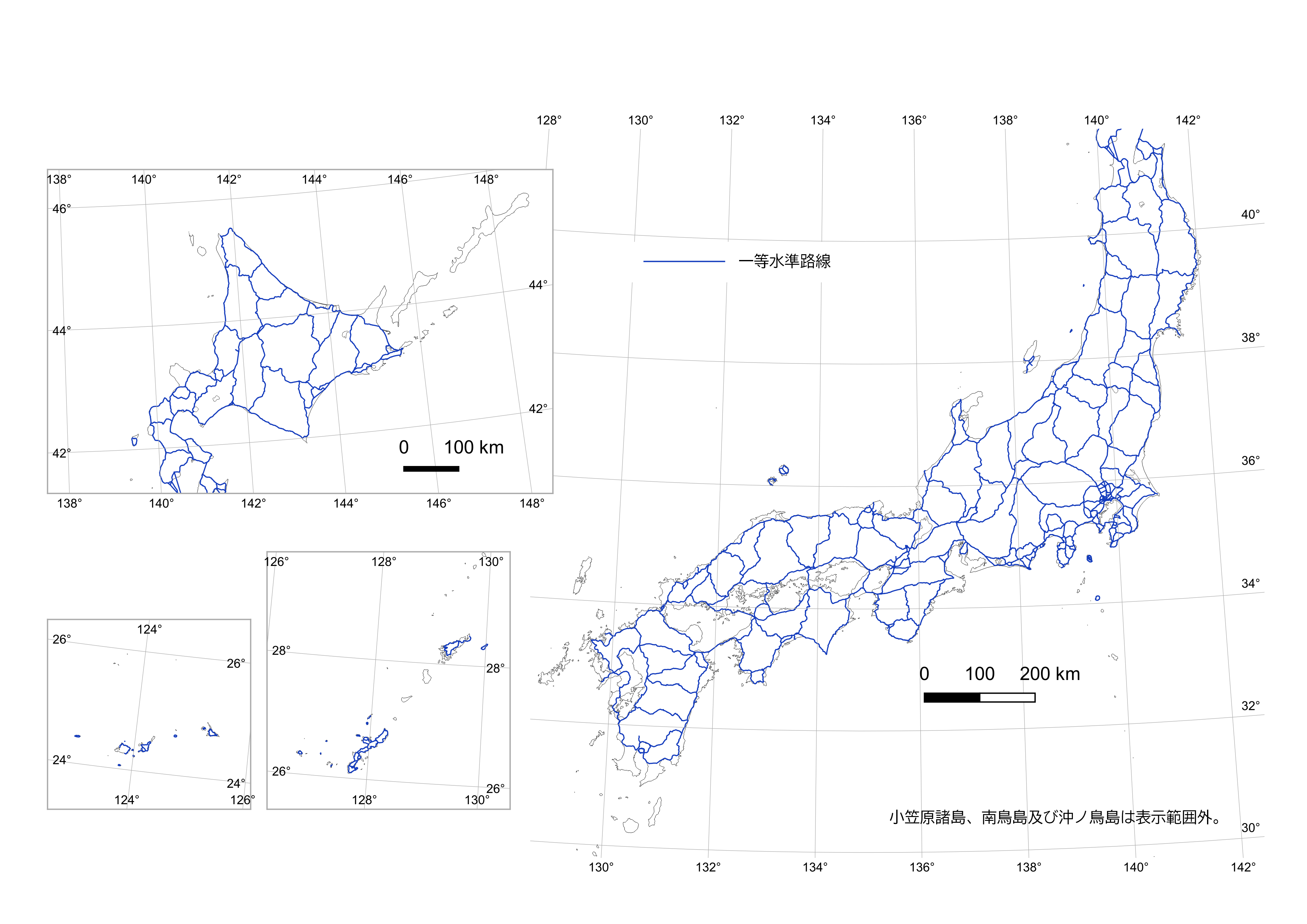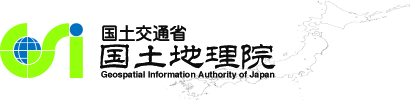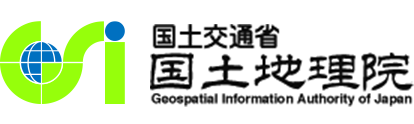水準点の測量
|
|
水準測量
水準測量は、標高の成果を有する水準点に基づき、水準点間の高低差を測定し、水準点の標高成果を得る測量をいいます。
2地点に標尺(長いものさし)を立て、その中間にレベル(水準儀)を水平に整置して、2つの標尺の目盛りを読み、その差から高低差を求める測量を直接水準といいます。この繰り返しで、水準点間の高さを求めます。精密な水準測量では、高低差を0.1ミリメートル単位まで計測しています。
水準測量に使用される測量機器は進化を遂げましたが、高精度に高さを求める基本的な測量方法は今も昔と変わっていません。レベルと標尺間の距離を等しくしたり、レベルの据え回数を偶数回にするなどの工夫をして誤差を小さくしています。
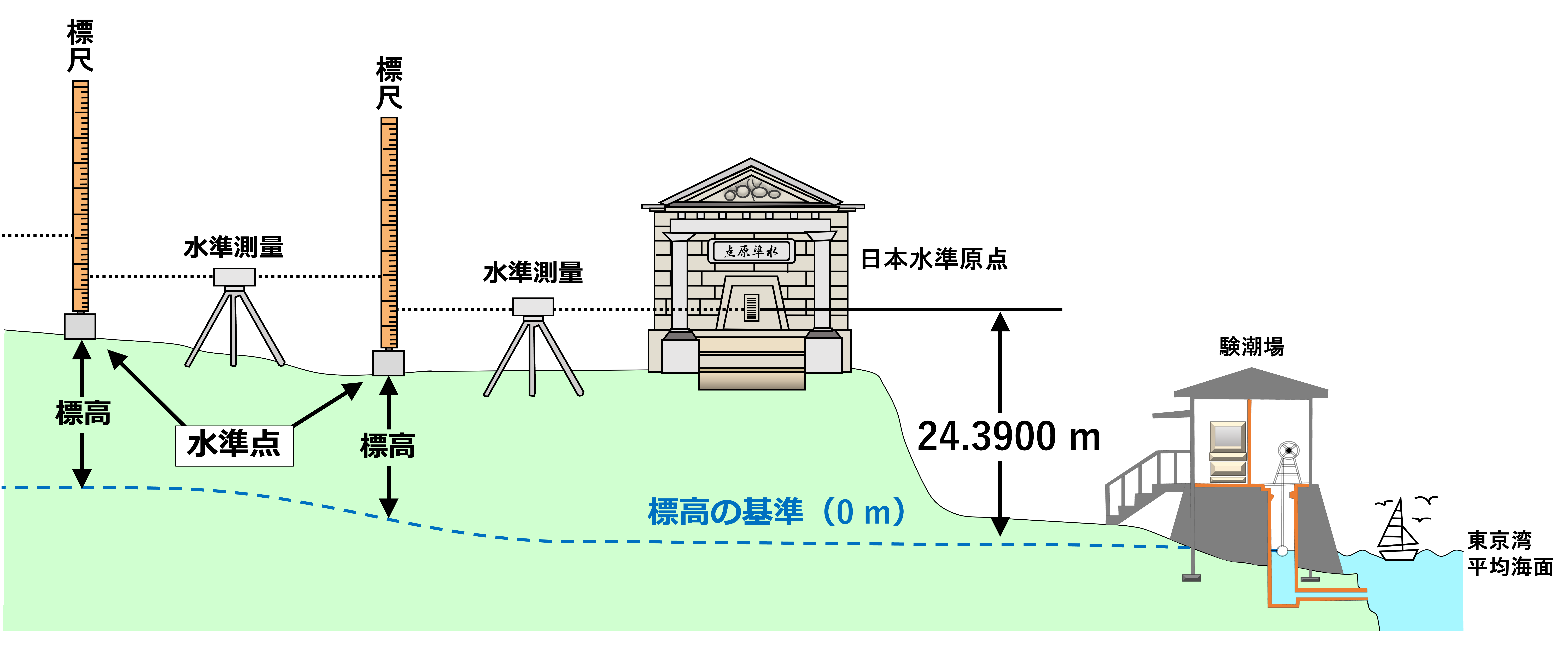 水準測量(東京湾平均海面から水準点まで)
水準測量(東京湾平均海面から水準点まで)
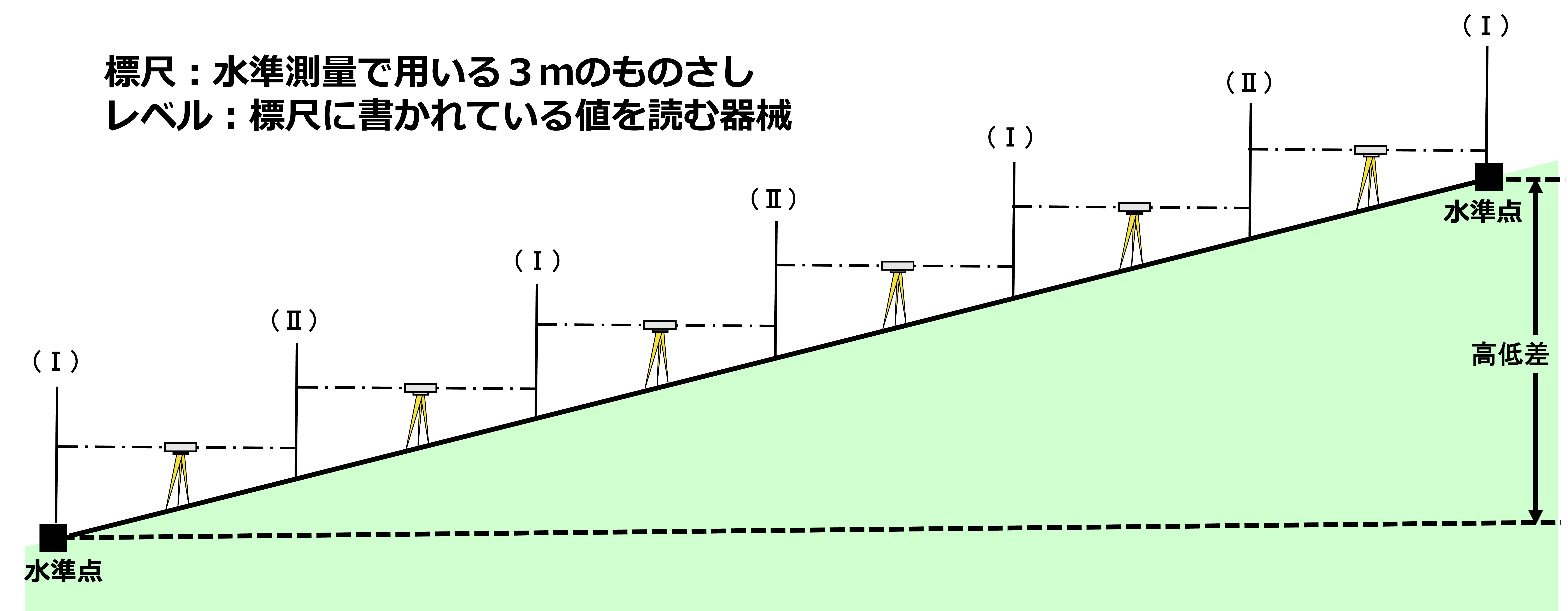 水準測量(水準点から水準点)
水準測量(水準点から水準点)
レベルは、気泡管(ティルティング)レベル、自動レベル、電子レベルと時代とともに進化してきました。現在、主力として使用されているのは、電子レベルとバーコード標尺の組合せです。日射による温度上昇を避けるため、日傘を差して観測をしています。
 測量風景
測量風景
水準点の測量成果(標高)の位置は、水準点の頭頂部分半球状の突起部分(球分体の頂上部分)です。標尺(おおきなものさし)を、水準点に対してまっすぐ直立にセットします。水準点でない場所では、標尺台と呼ばれる白色の台座を地面の上に踏み固めて設置し、その上に標尺をセットします。
標尺は、数値の目盛りを直接読定するタイプとバーコードにより画像判読するタイプがあります。熱による膨張を小さくするため、目盛り部分にはインバール等の材質が使用されています。
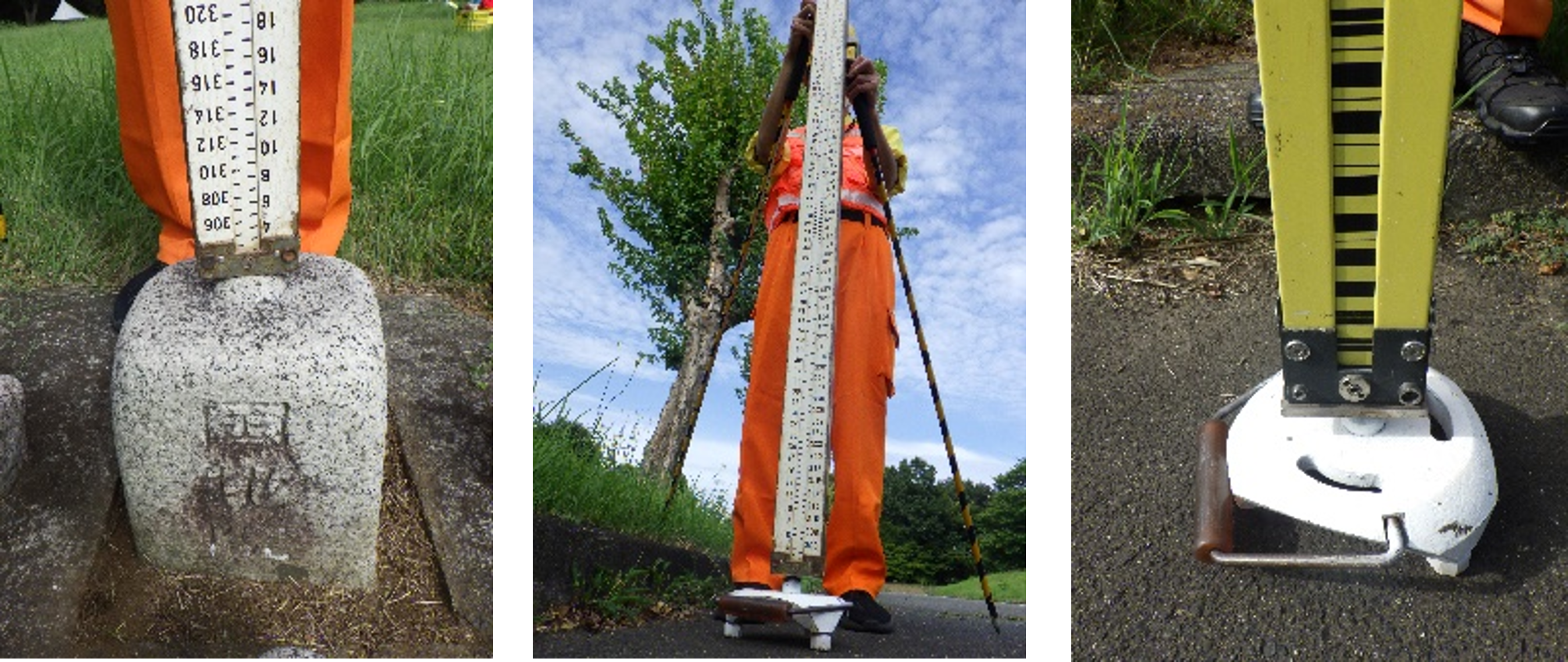 標尺及び標尺台
標尺及び標尺台
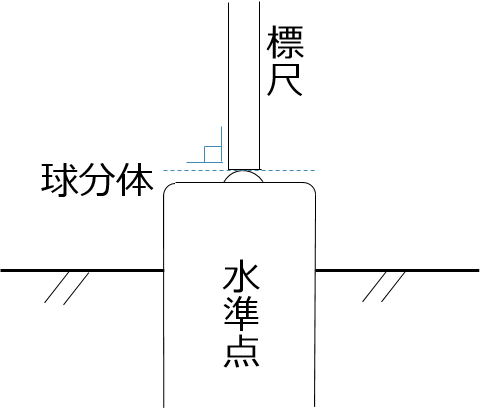 模式図 水準点 球分体 標尺
模式図 水準点 球分体 標尺
水準点は、全国の主要国道等に約2キロメートルごとに設置されており、これを水準路線といいます。国土地理院では、約16000点の水準点を管理しています。
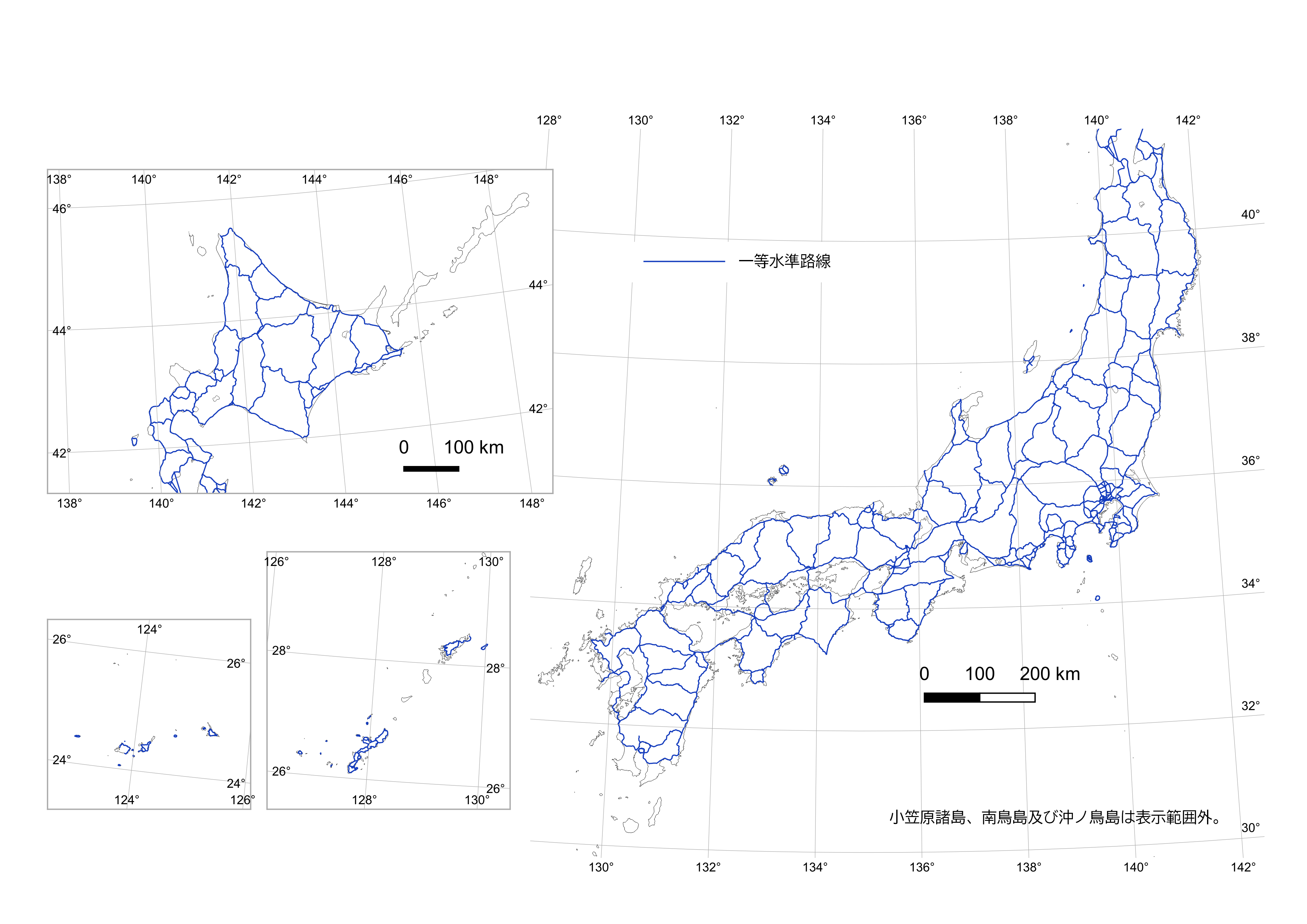 一等水準路線図
一等水準路線図
|