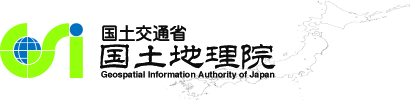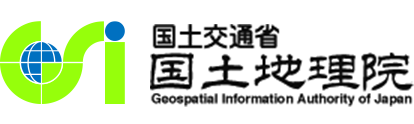令和4年度地理空間情報の活用推進に関する北陸地方産学官連絡会議「石川県分科会」を開催
令和4年度地理空間情報の活用推進に関する北陸地方産学官連絡会議「石川県分科会」を開催
令和5年度「地理空間情報の活用推進に関する北陸地方産学官連絡会議『福井県分科会』」(以下「分科会」という。)を11月30日(木)にWeb会議形式で開催し、構成員、講演者及び福井県内自治体の方を含め、27名が出席しました。
会議概要
分科会は富山大学の大西教授が座長として議事を進行し、地理空間情報の活用や福井県内で行われている先進的な取り組みについての講演とともに、その内容に関して意見交換が行われました。
1.講演
(1)福井県民衛星すいせんの画像を用いた土砂災害対策支援
講演者:福井工業高等専門学校 環境都市工学科教授 辻野 和彦
概要:近年多発している土砂災害について、衛星画像を用いてハード対策を施す優先順位決定の基礎情報となる土砂災害発生危険度算出を目指した実証結果について
(2)高精度な三次元点群データを用いた地形の面的変状解析及び三次元点群データを用いた活用事例紹介
講演者:株式会社サンワコン 萩原 春親
概要:周辺に多数の地すべり地形が確認されている地域で、高規格道路の法面と盛土の変状把握を高精度な三次元点群測量で行った結果と、インフラの維持管理や設計における三次元点群データの活用事例紹介
(3)永平寺町におけるレベル4自動運転の取組
講演者:永平寺町 総合政策課 課長補佐 山村 徹
概要:国内初の自動運転車によるレベル4運行について、取り組むに至った行政上の背景と課題を紹介
敬称略
講演者:福井工業高等専門学校 環境都市工学科教授 辻野 和彦
概要:近年多発している土砂災害について、衛星画像を用いてハード対策を施す優先順位決定の基礎情報となる土砂災害発生危険度算出を目指した実証結果について
(2)高精度な三次元点群データを用いた地形の面的変状解析及び三次元点群データを用いた活用事例紹介
講演者:株式会社サンワコン 萩原 春親
概要:周辺に多数の地すべり地形が確認されている地域で、高規格道路の法面と盛土の変状把握を高精度な三次元点群測量で行った結果と、インフラの維持管理や設計における三次元点群データの活用事例紹介
(3)永平寺町におけるレベル4自動運転の取組
講演者:永平寺町 総合政策課 課長補佐 山村 徹
概要:国内初の自動運転車によるレベル4運行について、取り組むに至った行政上の背景と課題を紹介
敬称略
2.意見交換等
・衛星画像に対して用いた解析手法や解析に先立ち準備したデータの種類、解析で変位があった箇所において現地で高さの変化が確認できている箇所の有無
・地形の面的変状解析における精度検証位置について、三次元データのまま発注図等で使用する場合の技術的課題、点群データから平面図を作成する際の工夫
・自動運転における衛星測位での位置ずれの主たる原因、自動運転のビジネスへの展開
について、質問や意見があった。
・地形の面的変状解析における精度検証位置について、三次元データのまま発注図等で使用する場合の技術的課題、点群データから平面図を作成する際の工夫
・自動運転における衛星測位での位置ずれの主たる原因、自動運転のビジネスへの展開
について、質問や意見があった。